TopMenu

吉江雅祥
(元朝日新聞写真出版部長)
 一眼レフ時代の始まり『アサヒフレックス』
一眼レフ時代の始まり『アサヒフレックス』
『ニコンF』が発売されたのが昭和34年である37年前だ。キヤノンレフ第1号も昭和34年だ。一眼レフ時代はそのころから始まったと考える人が多いが、国産の一眼レフはその7年前から始動している。ペンタックスではない『アサヒフレックス』が昭和27年に発売されている。日本で初めての一眼レフカメラであった。
ペンタックスではないと言ったのは、数年たっておなじ旭光学から発売されたペンタックスはファインダーで正像を見ることが出来た。ペンタプリズムをつかっている現在の一眼レフはこれが当たり前のことだが、アサヒフレックスは上からファインダーをのぞき込んで撮影をする。
このカメラは発売されたときに買った。まだ写真を仕事にするかどうか迷っていたころで普通のサラリーマンをやっていた。朝日新聞出版写真部に入る2年前のことである。なぜかその時期に、カメラ雑誌はいっせいに一年ほど前に発売された東ドイツ製の一眼レフカメラ『エキザクタ』の紹介記事を載せていて、秀逸な性能と名声を報じていた。使っていた二眼レフカメラのパララックス(ファインダーレンズと撮影レンズの視野のズレ)に悩まされていて、エキザクタのようなタイプの一眼レフカメラを手に入れることが出来たら、素晴らしい写真が撮れるにちがいないと思っていた。カメラ雑誌『アルス』の北野邦雄さんなどがこのカメラをベ夕ほめしていて、ぞれにかぶれて、これからのカメラは一眼レフタイプになるのだと思いこまされたと言ったほうがよい。それから間もなく『アサヒフレックス』の広告が雑誌に載ると、我慢ができなくなって『ローライコード』を買うつもりの貯金でとびつくように買ってしまった。
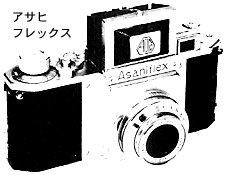 レンズをとおしてフィルムに写る大きさで映像をそのまま見るかとができる。もっとも、そのままと言っても左右逆像が見えるのだか、二眼レフカメラとは違った感じがして新鮮であった。動くものは追いかけにくいので、やたらと花のアップを撮影してよろこんでいた。と言うよりはファインダーをのぞき込んで楽しんでいた。
レンズをとおしてフィルムに写る大きさで映像をそのまま見るかとができる。もっとも、そのままと言っても左右逆像が見えるのだか、二眼レフカメラとは違った感じがして新鮮であった。動くものは追いかけにくいので、やたらと花のアップを撮影してよろこんでいた。と言うよりはファインダーをのぞき込んで楽しんでいた。
アサヒフレックスには50ミリf3.5のレンズがついていたが、絞りにオート機構がついていなかった。くわしく言うと、現在の一眼レフカメラはシャッターボタン押すとミラーが上がり、絞りか動き、シャッターが切れ、そのあと絞りがふたたび開放になる。そうしてミラーが元の位置にもどるのか当たり前のことだが、当時のカメラはそんな親切なことはとてもしてくれなかった。せいぜいオート・プリセットと言って、あらかじめ使用する絞り値にセットしておいて開放絞りでピントを合わせ、リングを回すことで使用絞り値で止まるようにする機構かつくのだが、最初のアサヒフレックスにはそれもついていなかったから撮影までの手順が面倒であった。
一ケ月ほど持ち歩いているうちに、どうにもならない欠点かあって使うのをやめることになる。欠点というのはシャッターが重いことである。理由はエバーセット方式と言って反射ミラーはシヤヅターボタンを押している間上がっていて、指をはなすと下がる方式であったから、シャッターボタンがやたらと固くミラーを押さえるためにかなりの指の力が必要だった。おおげさな言い方をすると、つづけて10枚ほどシャッターを押すと、ひとさし指か痛くなりどうにも我慢ができなくなってしまう。休日に野外にでかけ、一日夢中になって写真を撮り歩いたら、たまたま深爪をしたのと重なり、指が痛み数日、字も書けないほど腫れあがってしまった。それならばとレリーズをつかうとレリーズがすぐこわれてしまうのだ。
このカメラの評判が当時どうであったかよく覚えていないのだが、このあと旭光学はクイックリターン方式のIIB型を発表し、さらにペンタプリズムをつけた一眼レフカメラ『アサヒペンタックス』をつくり出すことになる。これは最初のカメラに対する評判や不満をしっかり聞いたからだろう。使用者の希望や要求を聞くことによりカメラの性能はよくなり、ペンタックスと言う画期的なベストセラー・カメラを生み出した。
しかし、このことで私にとって旭光学のカメラは苦手で無縁のカメラになってしまった。とにかくひとさし指の痛みという肉体的苦痛が思い出されてしまい何故か食欲がなくなってしまうのだ。以降この会社のカメラを買ったことはない。カメラにかきらずどんな製品でも、一度不愉快な思いを味あうと心理的に受けつけなくなってしまうようだ。
人がカメラを選ぶときには機能の良さも考えるが、スタイルを含めて人間にあたえる心理的な何かが影響する。航空機ファンならご存じの航空宇宙評論家・佐貫亦男さんの著書「飛行機のスタイリング」(グリーンアロー出版社・96年3月刊)は、飛行機のよいスタイルとは何かを論じている。
そのなかで佐貫さんは
「飛行機はライト兄弟の初飛行以来、計算と実験によって機能を求め最新の技術で性能を求めていけば、おのずから優れたスタイルができあがるように思われてきたが、それだけで優れたスタイルになるとは限らない。すぐれた飛行機のスタイリングは、搭乗者の精神を高揚させ自信を確保するものでなければいけない」
「つまり飛ばしたい、搭乗したいという気をおこさせ、目的によって、この飛行機ならばほかのどの飛行機にも負けないと言う自信を持たせるものでなければいけない。スタイリングは人間の精神を奮いたたせる動機である」
と主張している。
これを読んでいて、カメラにも同じところがあるなあと考えるのは私だけではないと思う。撮りたいという気持ちを起こさせるカメラ。佐貫さんは勇気を起こさせると言っているが、カメラにもこのカメラなら写せる、写ると言う勇気をおこさせ、奮い立たせてくれる機械がある。しかし一方、写欲を萎えさせてしまうようなカメラもあるのだ。

 一眼レフ時代の始まり『アサヒフレックス』
一眼レフ時代の始まり『アサヒフレックス』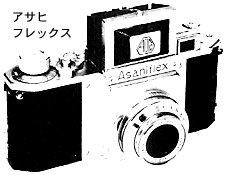 レンズをとおしてフィルムに写る大きさで映像をそのまま見るかとができる。もっとも、そのままと言っても左右逆像が見えるのだか、二眼レフカメラとは違った感じがして新鮮であった。動くものは追いかけにくいので、やたらと花のアップを撮影してよろこんでいた。と言うよりはファインダーをのぞき込んで楽しんでいた。
レンズをとおしてフィルムに写る大きさで映像をそのまま見るかとができる。もっとも、そのままと言っても左右逆像が見えるのだか、二眼レフカメラとは違った感じがして新鮮であった。動くものは追いかけにくいので、やたらと花のアップを撮影してよろこんでいた。と言うよりはファインダーをのぞき込んで楽しんでいた。