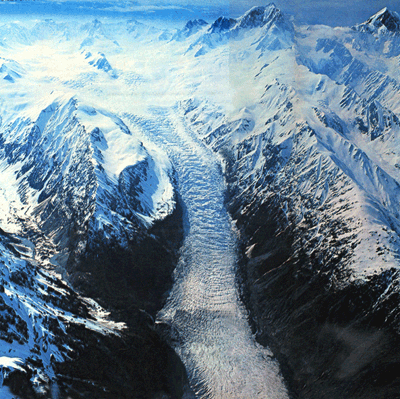 初めての体験だった。二つの小学校を撮影し終わったときはふらふらだった。多分顔は真っ青になっていたのだろう。Tさんが「羽田に帰るよと言ったときは、ほっとした」Tさんは社に帰る私に撮影が失敗だったらすぐ連絡しなさい、もう一度飛びましょうと言ってくれた。
初めての体験だった。二つの小学校を撮影し終わったときはふらふらだった。多分顔は真っ青になっていたのだろう。Tさんが「羽田に帰るよと言ったときは、ほっとした」Tさんは社に帰る私に撮影が失敗だったらすぐ連絡しなさい、もう一度飛びましょうと言ってくれた。
 20世紀なかば日本は敗戦国であった。1952年昭和27年4月のサンフランシスコ平和条約が発効するまで日本は航空機を 持つことも、飛ばすことも出来なかった。朝日新聞には戦前から航空部があって自社の飛行機があったが、敗戦から7年間航空機を利用することは出来なかった。昭和27年平和条約が発効すると航空部が再開して活動をはじめた。
20世紀なかば日本は敗戦国であった。1952年昭和27年4月のサンフランシスコ平和条約が発効するまで日本は航空機を 持つことも、飛ばすことも出来なかった。朝日新聞には戦前から航空部があって自社の飛行機があったが、敗戦から7年間航空機を利用することは出来なかった。昭和27年平和条約が発効すると航空部が再開して活動をはじめた。筆者が朝日新聞社に入ったのは昭和29年だから、戦後の航空再開から2年経っていた。そのころは何か事件や事故があれば、まず飛行機を飛ばすという態勢になっていて、新聞写真部員が羽田にある朝日新聞格納庫に交代で常駐していた。われわれ出版写真部員もいろいろな機会に航空撮影の仕事が多かった。
初めて社の飛行機にのったのは入社して3ヶ月くらい経ったとき、朝、出勤するとデスクが「吉江君は航空撮影をやったことがあったかな、ない。それなら勉強のために今日は羽田に行ってくれ。たいした仕事ではない。週刊朝日で羽田空港の写真が必要になった。飛び上がってちょっと撮影すれば10分ですむ簡単な仕事だ。すぐ出かけてくれ、航空部には新米カメラマンが行くからよろしく指導してくれと頼んでおく」
入社間もない新米カメラマンの筆者は、航空撮影の経験はない。でも先輩たちが航空撮影の時は大判カメラで撮影していることは知っていた。手札判のパルモスを使っていたのだが、デスクは4×5判のスピグラを持ってゆけと言ってピカピカのスピグラを貸してくれた。カメラには興味があったので先輩のスピグラを何回も借りてはてテストしていたから借り物のスピグラの操作に迷うことはなかった。
羽田に到着すると航空部のTさんというベテランパイロット(この人は平和条約締結前にアメリカに行って操縦の訓練をうけ、ライセンスを取っていた)が待ち受けていて「はじめてなのでよろしくお願いします」と挨拶すると「撮る目標を見失なはないように、飛行機は写真を撮り安いように操縦すらから心配はない。ここと思うところでシャッターを切りなさい」と言ってくれた。
最初に乗った飛行機の機種をどうしても思い出さないのだが、多分単発のセスナ機だったはずだ。「羽田空港の撮影は特別な許可がいるしばらく上空で待機していて管制塔の許可が出たら旋回して撮影位置に向かう」と言って離陸し2、30分、東京湾上空を旋回した。
上空からの撮影だったので、あっけないほど簡単に空港の撮影が済んだ。すぐ着陸するのかと思ったら、Tさんが「新聞の仕事で小学校を二つ撮影する仕事が無線ではいった」「簡単な撮影だから着陸前にちょっと撮ってちょうだい」といって山梨県の小学校を撮影することになった。
小学校の撮影は羽田空港を撮影するような簡単なことではなかった。鉄道の線路伝いに小学校のある町を探して撮影が始まった。学校を東西南北、四方から撮影する。上空500メートルくらいから急降下して急旋回。上昇する直前にシャッターを切る。目標の小学校をしっかり見つめていると天地がひっくり返り、急に大地が眼前に迫ってくる。シャッターを切るのがやっとだった。
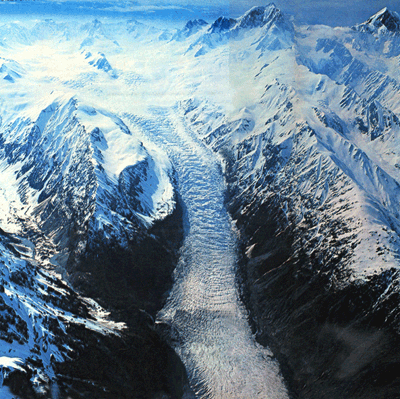 初めての体験だった。二つの小学校を撮影し終わったときはふらふらだった。多分顔は真っ青になっていたのだろう。Tさんが「羽田に帰るよと言ったときは、ほっとした」Tさんは社に帰る私に撮影が失敗だったらすぐ連絡しなさい、もう一度飛びましょうと言ってくれた。
初めての体験だった。二つの小学校を撮影し終わったときはふらふらだった。多分顔は真っ青になっていたのだろう。Tさんが「羽田に帰るよと言ったときは、ほっとした」Tさんは社に帰る私に撮影が失敗だったらすぐ連絡しなさい、もう一度飛びましょうと言ってくれた。
後から聞くと、あれは出版写真部のデスクと航空部の了解で新米カメラマンが航空撮影が出来るかどうかのテストだった。社にかえってフィルムを現像してみると、どうやらどの写真もブレずに、しっかりと撮れていた。テストはパスしたらしい。
それが航空撮影体験のはじまりだった。それから間もなく週刊朝日がカラーページで日本風船旅行の連載企画をはじめた。航空撮影と言うだけで珍しがられた時代は過ぎていたが、空中撮影の手法を変えることで空中撮影写真が新しい表現を発見していた時代であった。
それまで航空撮影というと対象物を画面に入れ斜めのごく普通の角度から撮影した写真が空中写真の典型だった。つまり画面に水平線や地平線がはいる俯瞰写真である。新しい手法の一つは対象物を真上から撮影することだった。いまはグーグルアースで真上からの空中写真はいくらでも見ることが出来るから珍しくもないが当時はそんな空中写真はあまり見かけなかった。
ヘリコプターで撮影すると機体から身体を乗り出すことで比較的簡単に出来ることであったが、プロペラ飛行機ではこの角度で撮影するためには、機体を旋回して傾け地面に直角にしなければならなかった。双発のエンジン機で新聞の投下用の機体下部の窓を開けて撮る方法もあったが一般的ではなかった。
真上から撮影の空中写真ははじめは苦労したが、カメラマンの意図が正確に伝わり、撮影した写真が雑誌に掲載されるようになると、パイロットたちはこちらの要求希望をうまく消化してくれて、カメラマンが撮影しやすいように操縦してくれた。
空中写真はカメラマンが写真を撮ったように思われているが、実は撮影ポジションはカメラマンが決めることができない。飛行機やヘリコプターのパイロットがその位置にカメラをもっていってはじめて写真が撮れるのだ。撮影ポジションの決定という点ではパイロットが半分以上撮影しているようなものだ。
対象物をどういう角度から、どのように撮影するかをパイロットに伝えることが空中写真ではまず必要だ。これがないとパイロットはいままでの経験から多分この程度の写真でよいだろうと思って機体を操作する。これではほとんどパイロットが撮った写真になってしまう。
この原則はグライダーでの撮影、単発のセスナ機から双発のジェット機あるいはヘリコプターに至るまで同じことである。これは国内だけでなく海外で空中撮影をする場合もおなじことだ。
60年代になって,海外での航空撮影が始まったときも、朝日新聞社航空部のパイロットたちとの取材経験があったから、飛行前にパイロットと打ち合わせがうまくいけば大丈夫とということであまり心配することはなかった。
はじめ航空撮影では4×5判フィルム使用の大型カメラを使ったが、間もなく120フィルム使用のブロニカに変わった。そのあと出版写真部ではハッセルブラッドを使用することになるが、ハッセルのシャッタースピード公称500分の1秒が実測300分の1秒くらいしかなくこれを嫌ってブロニカを愛用する人もいた。
写真説明
(1)アサヒグラフでイタリア風船旅行を連載した。
ローマ・コロッセオ(古代の円形闘技場)
ブロニカ・ニッコール200ミリで撮影
(2)オーストラリア・ニュージーランドでの航空撮
ニュージーランド南島フォックス氷河
ブロニカ・ニッコール135ミリで撮影