 この問題は新聞では各紙がカラー印刷をするようになって、ネガカラーフィルムの自動現像機を何台も設置することで解決されたように見えた時代があった。新聞社のカメラマンの常用フィルムがネガカラーフィルムになったのだ。これは写真の実用の歴史のなかの一齣である。これは昭和おしまいに近かったの頃の話である。
この問題は新聞では各紙がカラー印刷をするようになって、ネガカラーフィルムの自動現像機を何台も設置することで解決されたように見えた時代があった。新聞社のカメラマンの常用フィルムがネガカラーフィルムになったのだ。これは写真の実用の歴史のなかの一齣である。これは昭和おしまいに近かったの頃の話である。
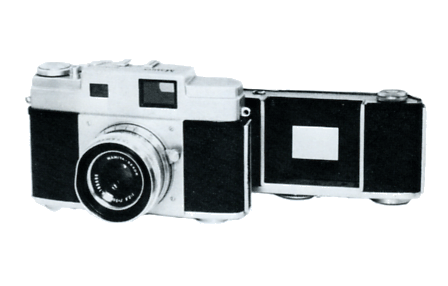 写真を写していて、カラーフィルムで撮影するか、モノクロフィルムで撮影するか大いに迷った時代があった。まだ新聞では写真のカラー印刷がほとんど行われていなかった頃のことである。
写真を写していて、カラーフィルムで撮影するか、モノクロフィルムで撮影するか大いに迷った時代があった。まだ新聞では写真のカラー印刷がほとんど行われていなかった頃のことである。これは雑誌の仕事をしていたカメラマンの話である。大きな事件や、ニュース写真の取材していた雑誌カメラマンは一つの瞬間をカラーフィルムで撮るか白黒で撮影するかで迷った。理由は雑誌の仕事は通常ページの割り振りはあらかじめきまって取材していることが多く、それがモノクログラビアページなのかカラーページなのかもきまっている場合が多かった。
取材前からあらかじめ指定されているからモノクロと決まっているならば迷わず白黒フィルムで撮ればいいのだが、事件や大きな出来事の取材になるとページ数もきまっていないし、白黒グラビアかカラー写真が使われるかは流動的で全くわからない。編集部は事態が大きくなればカラーも使うしページ数も増えてくることになる。ときにはカラーモノクログラビアに記事ページをたくさん割くこともある。ときには別冊特集でそのニュースを扱うこともある。
とくに週刊誌の場合は締め切り日の関係で流動的だ。言い方を変えれば、どんな場合でもカラー、モノクロ両方の写真を手持ちにしておきたいのが、編集部の気持ちだ。ところが写す方にとってはこのかけがえのない瞬間に、一瞬どちらで撮るかが問題になってくる。
そんなことに迷うことはないんじゃーない、カラーで撮っておけば問題ないのでというのが今の常識だが、と書いて考えてしまう。デジタルカメラではそんなことを問題にすること自体がおかしい。モノクロ設定で撮ることも出来るが、カラーで撮っていればモノクロ出力も簡単なことだから、そんなことは考えないだろう。
当時は締め切り間際のときにはカラーフィルムで撮影したものを現像して、モノクロに作り替えるのに時間がかかった。カラーフィルムの現像に時間がかかったし、カラーからのモノクロ反転技術がいい加減であったからモノクロ写真として印刷するとかなり質が落ちた。このことでは朝日出版写真部ではカラーフィルムからの反転モノクロをいかに質を上げるかで技術系の写真部員が何年もかかっていろいろな装置を作っていた。
プロのカメラマンがこの問題に悩んだのは昭和30年代はじめから40年代であった。ピークというよりこの問題が大事(おおごと)になったのは東京オリンピックの時であったと思う。東京オリンピックでは各競技の取材が制限された。各新聞社が何人ものカメラマンをたくさん配置して白黒カラーをそれぞれ撮るような人海戦術はとれなかった。
一人のカメラマンがカラーとモノクロの2台のカメラをもっていったとしても、ワンチャンス(最良の瞬間)のでシャッターは2度切ることは出来ない。各社がこのためいろいろ工夫してカメラををつくった。
今記憶しているのはニコンを縦に並べてシャッター軸を結び一台のシャッターボタンを押すことで同時に2 台のカメラのシャッターを切ると言うのがあった。これは毎日新聞の写真部員がニコンに作らせて最初にこのカメラを使った。この亜流で2台のカメラを縦に固定し、シャッターが同時に切れるだけでなく、レンズのヘリコイドをギアで直結して同時にピント合わせをする機構を持ったカメラが作られた。各社がいろいろ工夫をしていることはカメラメーカーからの情報でわかった。
取材で三脚を立てることが出来る場合は、カメラを2台並べレリーズで同時に2台のカメラのシャッターを切るなどは当たり前すぎて話題にもならなかった。新聞の場合は撮影から印刷までの時間をいかに縮めるかで競争をしていたからカラーフィルムで撮ってという想定は時間的に許されなかった。
 この問題は新聞では各紙がカラー印刷をするようになって、ネガカラーフィルムの自動現像機を何台も設置することで解決されたように見えた時代があった。新聞社のカメラマンの常用フィルムがネガカラーフィルムになったのだ。これは写真の実用の歴史のなかの一齣である。これは昭和おしまいに近かったの頃の話である。
この問題は新聞では各紙がカラー印刷をするようになって、ネガカラーフィルムの自動現像機を何台も設置することで解決されたように見えた時代があった。新聞社のカメラマンの常用フィルムがネガカラーフィルムになったのだ。これは写真の実用の歴史のなかの一齣である。これは昭和おしまいに近かったの頃の話である。
随分昔のことのように思われるが、わずか20年ほど前の話だ。いまカラーかモノクロかなど、こんな話をすると笑われてしまう。デジタルフォトになってこの問題は完全に消えてしまった。でもあの時代には結構真剣に考えたものだ。
一台のカメラで白黒フィルム、カラーフィルム両方の撮影をする工夫はカメラメーカーのほうにもあって、よくもこんな馬鹿なことを考えたものだというカメラが発売されたことがあるのだ。マミヤ・マガジン35である。
出版写真部の先輩の大束元さん(この人は戦後間もなく月明の富士を発表するなど種々写真の新しい表現を試みた有名写真家であった)が、戦前マミヤシックスを作ったマミヤ光機の間宮精一氏と知り合いであった関係で、マミヤがつくる新しいカメラが大束さんを通じて出版写真部に持ち込まれていた。
マミヤではレンズシャッター付きの35ミリカメラは昭和20年代から製造していた。マミヤ35は昭和20年代後半には発売されていたし、2眼レフのマミヤプロフェッショナルが昭和32年に発売された。このカメラは写真部でもすぐ購入していたから、マミヤの技術の人がしょっちゅう写真部に出入りしていた。
ちょうどそのころ、マミヤは新考案カメラをつぎつぎ発表していた時期だった。レンズを交換するマミヤプロフェッショナル2眼レフもそうだが不思議なアイデアのカメラが作られた。記憶がすこしずれるかも知れないが、マミヤスケッチという24×24判サイズ35ミリフィルムを売り出したし、その当時は無かったフラッシュ内蔵のマミヤオートマチック35の発売も記憶がある。
35ミリカメラ、マミヤワイドWが35ミリF2.8レンズ付きで売り出されたのも同時期だった。このカメラには距離計連動式と目測で主点を合わせる型と両方あった。そんな新機種を次々発表していたときに、マミヤマガジン35が持ち込まれた。
一台のカメラで白黒フィルムとカラーフィルムを二つのマガジンに分けて、必要に応じて付けかえて撮影するというアイデアだった。これはいささかカメラマンの要求を先取りしすぎた感があった。アマチュアカメラマンはまだカラー写真を撮っていなかった。
プロのカメラマンがやっとカラー印刷の対応を考え始めたころだった。プロのカメラマンがカラーかモノクロかを考え始めた時期でもあった。
マミヤマガジン35は連動距離計がついた35ミリフィルム使用のカメラだった。レンズは直進ヘリコイドでセコールというこれは世田谷光機製の50ミリf2.8であった。レンズシャッターでセイコウシャ製の1-500分の1秒がついていた。ボディはアルミダイキャストでしっかりつくられていた。一見するとごく当たり前の標準レンズ付きレンジファインダー35ミリカメラだった。
何故このカメラのことを思い出したかというと、小生宅に写真の勉強で出入りしている学生が先月、「先生こんなカメラを知り合いからもらったのですがご存じですか」とマミヤマガジン35をもってあらわれたからである。
このカメラはごく当たり前のかたちをした35ミリカメラだがフィルムが入るマガジン部分がはずれてマガジンを交換することでフィルム部分を交換することが出来た。持ち込まれたマミヤマガジン35には交換マガジンがついていなかった。
 レンズ部分と距離計部分、フィルム巻き上げレバーなどがついたボディと、フィルムを装填する部分とフィルム巻き戻し機構のボディが分離して二つに分かれた。もう1個のマガジンボディがあれば異なった種類のフィルムを入れることでカラーとモノクロの交換が簡単に出来るカメラだった。
レンズ部分と距離計部分、フィルム巻き上げレバーなどがついたボディと、フィルムを装填する部分とフィルム巻き戻し機構のボディが分離して二つに分かれた。もう1個のマガジンボディがあれば異なった種類のフィルムを入れることでカラーとモノクロの交換が簡単に出来るカメラだった。
このカメラをもらった学生はマガジン部分のロックダイアルを回すことで簡単にボディが 分かれることは、実際に動かしてわかっていたが、何故ボディが二つに分かれるのか理由はわかっていなかった。
これがフィルムを無駄にしないでマガジンを入れ替えるための機構だと知ってびっくりしていた。確かに予備のマガジンが無ければそんんことに気づくはずはない。このカメラは売れなかった。マミヤの人もあれは失敗でしたと言っていた記憶がある。
このカメラをゲットした学生は親戚のご老人からもらったと言っていたが、当時こんなおかしなカメラを買っている愛好家がいるんですね、そんなに安いカメラではなかった。戦前からのマミヤシックスの熱狂的フアンがいたし、マミヤ愛好家、マミヤカメラフアンはたくさんいたから、マガジン35を買った人がいても不思議はないのかも知れない。
大束元さんがこのカメラをテストしてみるなら使ってご覧と貸してくれた。大束元さんは自分はこのカメラに全く興味が無い。代わりにテストしてみてよ、くらいの感じだった。1ヶ月くらいほうぼうに持ち歩いた。結論としてはこのカメラを使うよりは多少重くてもカメラを2台持ち歩く方が良いだった。
写真説明
(1)マミヤマガジン35 レンズ・セコールF2.8 50ミリ 昭和32年発売になっている。
(2)マミヤ35 このカメラには小西六のヘキサーレンズがついていた。昭和20年代半ばに発売。
(3)マミヤスケッチ 24×24判カメラ レンズは35ミリF2.8がついていた。このカメラはマガジンと同時期に発売された。