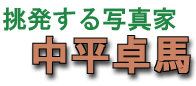
[1]写真家のパラドックス
「なぜ、植物図鑑か」以降の中平は写真から自らの「手の痕跡」を消し去ることで、表現としての写真に背を向け、そのために暗室作業を伴わないカラー写真による植物図鑑を方法として提示するが、東大安田講堂攻防戦や松永事件などによって写真を撮るという行為の暴力性、犯罪性にふれてしまい、撮影行為自体を否定せざるを得なくなってゆく。そしてのちに、彼の言葉が写真を縛り、行動をも縛っていった。彼は自らを固定された視点により遠近法的に世界と対峙する「権力」とみなした。そして、その視点は現実から断ち切られた不動の視点であり、「一点透視法にもとづいて世界を統御しようとする」権力の視点であった(※41)。ノイズだらけのこの世界、中平にいわせるなら「僕ら一人一人がめちゃくちゃに生きるこの地球上」(※42)をあたかも整然と秩序づけられた安定した場所であるかのように提示する写真を拒否し、彼自身「生きていく中で火急なる現実として立ち現れてきた括弧抜きの現実」(※43)である記録としての写真(中平が「記録」というとき、それは写真が表現であることを拒否するという文脈であり、素朴なリアリズムではなかった)を、自分や他者に対して提出していこうとするのである。そして、記録としての写真、つまりカメラの受動性に固執するあまり、中平は自分を消していくという方法を取ろうとするのだが、現実から断ち切られた不動の視点であるカメラという近代的な装置(遠近法の発見にカメラオブスキュラが貢献したという文脈)によって、現実とコミットするような記録としての写真を志向したところに写真家としてのパラドックスがあった。そして、彼は近代の所産であるカメラによって風景を切り裂こうとしたが、そこにはその方法そのものが「風景の創出」へとつながってしまうという円環構造があった。『PROVOKE』の後、風景を切り裂くはずであったアレ・ブレの手法が風景化し、制度的な視覚にのみこまれてしまったことを思いださねばなるまい(※44)。これは文化のジレンマであるが、中平はこのようなジレンマに正面から立ち向かってしまったのであり、上野昂志がいうように中平の関わっていたのが写真であったために彼は実践的に苦しみ、事態はいっそうむき出しに現れたのである(※45)。
世界を人間の主体を光源とした遠近法から解き放ち、事物の視線を組織すること、これが「なぜ、植物図鑑か」以降の中平にとっての「火急なる」課題であった。事物の視線を組織するとは、文化的コードを離れた地点での視線の組織化(あるいは非組織化)であった。そして、それは事物の視線、すなわちカメラの眼によって可能であるといい切ってしまうのはいささか短絡的であろう。確かにカメラは事物という他者であり、写真の生成過程を人間的視覚の延長線上にではなく、半ば自然現象のようなものとして位置付けることは可能だろうが、すべての写真がアジェのようになるわけではないし、単純にカメラの視線を即事物の視線であるとしてしまうのであれば、中平があれほど苦しんだ理由に近づくこともできないだろう。なぜなら撮影行為とは撮影者である人間の主体的な能動的な行為ぬきにはありえないのだから。『決闘写真論』の中平の言葉を引用しよう。
「受容的」であるとは世界に向かって私を開くこと、世界に私を晒すこと、そして進んで私を解体させる勇気をもつということである。だが、この解体を通してしか私を再創造することもできないのだ。それは主体に対する世界の侵害を率先して求めてゆくということである。「受動的」であることと「能動的」であることはここの一点において統一されるはずである。世界は客観的なものではなく、私は堅牢なものでもない。相互に浸透し合う白熱する磁場、それが世界である。(※46)
そして私には世界と写真家が相互に浸透し合い白熱する磁場を生成させる行為がシャッターを切る行為のように思えてならない。確かに、写真家は世界を主体=客体の二元論に還元してしまうような近代的装置(暗箱)を携えてはいるが、「私」であると同時に世界の一部でもあることのできる写真家という身体は、主体=客体の二元論を超えて世界に対して働きかけ得るのではなかったか。 しかし、中平にとってシャッターボタンはあまりに重く、彼の「手の痕跡」は写真として残されることはなかった。
[2]「手の痕跡」としての写真:バフチャルとキャパ
「手の痕跡」という言葉を聞くと、私は盲目の写真家ユジェン・バフチャルを思い出してしまう。バフチャルは写真集『絶対的覗き魔』の中で次のように書いている。
決して手の届かないものへの夢が、ある日わたしに最初の写真を撮らせることになった。もちろん、芸術的な意図があってのことではない。写真の美学的な側面は、わたしにはぼんやりと分かる程度に過ぎない。撮影されたイメージのツルツルの表面は、わたしに何も語りかけてくれない。わたしには、まだ見えていた頃に出会った人物や風景の物理的痕跡しかないのである。つまり、わたしの視線は他人によって見られた写真のシュミラークルとして存在しているに過ぎないのだ。わたしには、この大いなる無用性こそが嬉しかったのである。(※47)
バフチャルの撮影行為において、眼はその本来の機能を果たすことができない。彼が写真を撮るうえで、決定的な拠り所となるのは、彼の作品のタイトルにもあるように「光の触覚」(※48)ではないだろうか。光が彼の周りにあふれていて、対象から発せられた光が世界の側から彼に触れにくる。彼には見えないが、このことを信じることによってのみ彼の撮影行為が成り立つのである。そして、その光を受けとめる装置がカメラであり、「世界が写真でできている」ことを信じて行う半ば儀式的行為がシャッターボタンを切るという行為なのではないだろうか。確かにバフチャルにとって撮影された写真のツルツルの表面は、彼に何も語りかけはしないかもしれないが、彼の視線は他人によって見られたシュミラークルとしては存在する。眼で確認することこそできないが、彼にも同じように外界の光が触れにきていることを、少なくとも世界がそのようにあるということを確認する作業が彼にとっての撮影行為のように思えてならない。バフチャルは眼ではなく、触れにくる世界からの光を全身で受けとめる。そして、最終的には手によって光を受けいれる(感光させる)。自分にも触れにきている光を暗闇の中で保証してくれるのはもしかしたら写真だけなのかもしれない。
距離と光の制御ができないというバフチャルのハンディキャップを無効にしたのがオートフォーカスと自動露出であったが、シャッターボタンを押すという行為だけは眼が見えようが見えまいが撮影行為には不可欠であり、写真家に残された唯一の手作業である。むしろ、眼など露光のその瞬間には必要ないといってしまってもいいのかもしれない。なぜなら写真家がシャッターボタンを押したその決定的な瞬間、つまりフィルムが光を受けとめ、像が形成されるその肝腎な時に、写真家は当の対象を見ていないのである。そして、それは一眼レフカメラに顕著である。なぜならフィルムに感光させるためにミラーが上がり、視界が遮られるためファインダー内は真っ暗になってしまうからであり、カメラが眼を開いた瞬間、写真家の方はまばたきをするように眼をつぶってしまうのである。撮影の瞬間、写真家は何を見るでもなく、何をするでもなく、白痴のようにただそこに立ち尽くすのみである。この矛盾、撮影者である自分以外に被写体という他者(対象)を必要としているということ、さらに像が形成されるまさにその瞬間、すべてをカメラに委ねるようにして何もしていない写真家という奇妙な存在が写真術発明以降、従来の芸術と呼ばれるものとの摩擦を引き起こしてきた要因の一つであろう。露光のその瞬間写真家にできることはプロヴォークの写真家たちのようにカメラをブレさせることぐらいかもしれない。港千尋がバブチャルの写真に対して「いったいこれらの写真を見て、そのイメージだけから、撮影した人が盲目であるかどうかを判断できるだろうか」(※49)と語っているように写真を見る者にとって撮影者が盲目であるかそうでないかの判断は不可能であるし、盲目であろうとなかろうと見るものにとって実はたいした問題ではないのかもしれない。撮影が行われたまさにその瞬間、対象を見ていなかった撮影者は印画紙に移されたイメージによって初めてその光景を目にするのであり、制作者であるとともに最初の鑑賞者となるのである。この意味で写真家はシャッターを切ったその瞬間、対象を見ている必要はなく、「すべての写真家は盲目的である」といってしまってもいいのかもしれない。なにも眼が重要でないなどといっているわけではなく、重要なのは写真家がそこにいて、眼によってではなく、手によって光を受けいれるのだということである。
もう一人、手の写真家として「最も偉大な戦争写真家」と呼ばれたロバート・キャパについて考えてみよう。キャパの写真についての印象を草森紳一は次のように語った。彼の写真から意図のようなもの(たとえば思想や造形的、絵画的のもの、思い入れなど)がまったく伝わってこず「キャパの写真はまるで白痴のようであった」といっている。(※50)これはキャパが構図などを選択できないほど被写体に接近していたことによるのであるが、草森は恐怖の極限の中でシャッターボタンを押すため作家的なものを失わざるをえなかったこと、つまりキャパが「自分を超えた存在」であったことが彼の写真の魅力なのだと語っている。キャパの写真は彼自身をも超えた文化の共示を離れた地点にあり、それがまさしく有人カメラによるものであるがゆえに我々を絶句させるのであるし、この一点によりキャパは他の凡庸な報道写真家たちと大きく距離を隔てるのである。
「そのときキャパの手はふるえていた」(※51)で有名なノルマンディー上陸作戦の写真が撮影されたときキャパは「コンタックスのファインダーから目を離さずに気違いのように次から次にシャッターを切った」(※52)と語っているが、この時キャパはあまりの恐怖のため、文字どおりシャッターを切り続けることによって視界を遮ってしまおうと、むしろ対象を見ない(まさしく目の前の現実を切り離す)ようにしていたのではなどと想像してしまう。撮影後キャパは気を失ってしまうのだが、それほどの極限状況の中でまともに対象を観察し、構図を考えるなどできはしないだろう。ほとんどすべてをカメラに任せ、対象から触れにくる光を受動的に受けとめるしかないのだ。しかし、ただ受動的なだけではなく、シャッターボタンだけは押さねばならない。この受動的であり、能動的な行為が撮影行為なのであって、震えてブレたノルマンディーの写真はまさしく「手の痕跡」以外の何ものでもなかった。写真家が「手の痕跡」を否定することはできない。なぜならシャッターを切るというのは写真家にとって根源的な行為であり、「手の痕跡」によってのみ写真家たりえるのだから…。しかし、中平卓馬は「手の痕跡」を否定するあまり、シャッターを切るという写真家にとってあたりまえの行為を凍結し、彼の「手と光の痕跡」であったはずのフィルムとプリントは彼自身の手によって燃やされる事となる(※53)。
(註)
(※41)中平卓馬、前掲書 1973 p.25 中平は近代芸術の方法である不動の視点に変わって無数の動く視点を導入したのがウィリアム・クラインであり、その挑戦の結果が『NEW YORK』(1957)でのブレやボケであったのではないかという。
(※42)多木、中平、前掲書 p.169
(※43)同上
(※44)スーザン・ソンタグは『写真論』の中でエドワード・ウェストンやポール・ストランドの前衛的な視覚もすぐに同化され異化の磁力を喪失してしまったことを指摘している。つまり、「風景を切り裂く」方法そのものが「風景の創出」(柄谷行人)へと帰着してしまうということ。
(※45)『写真装置』4号 特集「風景写真」よりp.63「風景という文脈」上野昂志
(※46)篠山、中平、 前掲書 p.149
(※47)『絶対的覗き魔』1992 p.15
(※48)被写体を暗闇の中においてシャッターを解放にし、光を少しずつ当てていき撮影された作品
(※49)港千尋『映像論<光の世紀>から<記憶の世紀>へ』(日本放送出版協会)1998、p.240
(※50)草森紳一『カメラ毎日』1968年10月号所収「行動と写真」 西井一夫は「キャパの白痴」とプロヴォークの写真家たちが使っていた「アノニマス(匿名性)」には重なる部分があると指摘している。
(※51)ロバート・キャパ『ちよっとピンぼけ』川添浩史・井上清一訳(文春文庫)1979 9章のタイトルが「そのときキャパの手はふるえていた」である。
(※52)同書 p.163 篠山紀信も『決闘写真論』の巻末の中平卓馬との対談で、いやなところへいったときほどシャッターを押し続けるというようなことをいっていた。
(※53)「私」だけでなく、これまでの写真家としての痕跡を消そうとする中平の思いは、彼をフィルムを燃やすという極端な行為にまで走らせた(フィルムを燃やすエピソードは『決闘写真論』の「インタープレリュード」の章に収められている)。オリジナルプリントが存在しないため、1989年に山口県立美術館で行われた写真展「11人の1965〜75 日本の写真は変えられたか」では写真集『来たるべき言葉のために』が解体され見開き貢を一点として展示された。